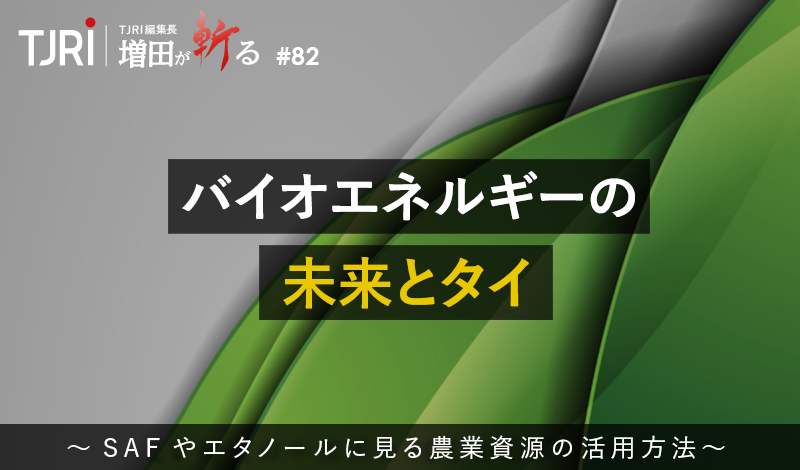バイオエネルギーの未来とタイ ~SAFやエタノールに見る農業資源の活用方法~ 公開日 2024.02.27
2022年11月15日号のこのコラムで、「バイオ燃料の復権はあるか」 というタイトルの記事を執筆した。その内容はタイでのキャッサバ原料のエタノール利用拡大を求める声と、バイオ燃料を抹殺した日本でも復活を模索する動きが出てきたことを紹介する内容だった。
そして、このコラムから1年半を経て、世界的にもエタノール、バイオディーゼルというバイオ燃料が再評価されつつある。それは、わずか1年あまり前まで自動車の動力源は電気になる、つまり内燃機関(ICE)車は駆逐されてすべて電気自動車(EV)になるとの論調が支配的だったのが、ここにきてこの論調が急速に変化してきたこととも関係している。さらに地球温暖化対策としての脱炭素化、電動化が難しい飛行機で、持続可能な航空燃料(SAF)の導入加速が待ったなしになってきたこともある。今週配信したBBGI社長インタビュー 、GBEPの国際会議 でもバイオ燃料、そしてエネルギーにおけるバイオ資源の重要性を知ることができる。
改めてタイの優位性 「ウボン・バイオエタノール(UBE)は新たに食品製造にフォーカスしているものの、依然、エタノール事業を継続していく計画で、政府にこのエタノールの利用促進を求めている」
今年1月13日付バンコク・ポストはビジネス2面で、UBEのスリーヨット社長インタビューに基づき同社の事業戦略を紹介する記事を掲載した。記事ではまず、UBEがキャッサバを原料とするエタノール製造企業から脱皮し、酵素などバイオ技術を利用した機能性食品など高付加価値製品の開発を目指していると説明。そして同氏が会長を務めるタピオカ・エタノール協会が、加工ハーブ業界や化粧品業界と連携して、「エタノール由来アルコールの自由取引」を推進していることを明らかにした。TJRI(タイ日投資リサーチ)では、既に同社についてはOpen Innovation Talk とスリーヨット社長インタビュー記事 で紹介済みだ。
そして、サトウキビから砂糖を精製した後の残さである廃糖蜜(モラセス)を原料とするエタノールのタイ国内メーカーとして、大手のミトポン、カセタイ・インターナショナル・シュガー(KTIS)に次ぐ生産量3位が今週のTJRIのインタビュー記事で紹介したBBGI だ。1月8日付バンコク・ポストはビジネス4面でバンチャク傘下のBBGIが持続可能な航空燃料(SAF)生産に取り組んでいることを改めて紹介しているが、そこではキッティポン社長はSAFの原料として使用済み食用油(廃食油)だけでなく、「次世代原料」を探したいとし、BBGIが提携するインドのFermbox Bioの「Alcohol-to-Jet(ATJ)」技術を活用すると説明している。このFermboxは「Synbio」製品の開発・生産を手掛けるインドの新興バイオ企業だ。ちなみにこのSynbioとはSynthetic Biology(合成生物学)の略字で、特に微生物など有機体を再設計する技術などの最先端のバイオ技術で、Fermboxは発酵技術に強みがあるようだ。
タイでのバイオテクノロジーの可能性 TJRIニュースレターでは、サトウキビ、キャッサバ、アブラヤシ(オイルパーム)などの商業作物が豊富で価格も安いことがタイの強みであり、バイオ産業に適していると何度も強調してきた。筆者も日系企業を含む幾つかのバイオ関連企業の開発・生産現場を取材することができた。植物由来のバイオマスを原料に独自の「微生物発酵」プロセスによる新しい構造タンパク質の製造方法を開発し、2022年7月にタイのラヨーン県の工場の操業を開始した山形県鶴岡市のベンチャー企業のスパイバー が、初の海外進出先にタイを選んだのは、サトウキビやキャッサバなど原料となる糖が豊富なためだ。そして、「非可食バイオマス」を用いたセルロース糖製造技術を開発し、2023年8月から試験生産・販売も始めた東レの子会社セルローシック・バイオマス・テクノロジー(CBT) も工場立地先としてサトウキビ畑と製糖工場が多いタイ東北部ウドンタニを選んだ。
さらに、タイの給油所運営大手PTGエナジーの子会社PPPグリーン・コンプレックス(PPPGC) が2019年に南部プラチュアブキリカン県で操業を開始したアブラヤシ(オイルパーム)を原料としてパーム油やバイオディーゼルなどを生産する先進的工場の見学では大きなインパクトを受けた。アブラヤシを原料とするパーム油とバイオディーゼル工場を見るのは初めてだったこともある。PPPGCの最新工場の規模の大きさと、食用油やエタノールよりも高付加価値の製品開発に取り組んでいる姿にバイオ分野でのタイの可能性の高さを実感し、タイ政府が打ち出したバイオ・循環型・グリーン(BCG)経済戦略の方向性の正しさを確認できた。
さらに、今週紹介した国連農業食糧機関(FAO)のプログラムである「GLOBAL BIOENERGY PARTNERSHIP」の年1回の国際会議「GBEP Bioenergy Week 」が昨年10月にバンコクで開催されたことも、アジア太平洋地域ではタイがバイオエネルギー分野で有望な国であることを示した形だ。現在はタイ国立科学技術開発庁(NSTDA)傘下で、タイのバイオ経済を推進するBIOTECが設立されたのが1983年と約40年前だったことを知って少し驚いた。そのBIOTECが主催する形で行われたフィールドトリップ先の国立キングモンクット工科大学トンブリ校(KMUTT)のバンクンティアンキャンパスで、キャッサバ原料のバイオエタノールの試験プラントや藻類をエネルギー資源化する研究施設やバイオガス施設などを見学し、タイが長年バイオ技術の研究に力を入れてきたことを確認した。
KMUTTの藻類資源化の研究施設 SAFはバイオ燃料の1つ バンチャクと傘下のBBGI、そして東レの子会社CBTもここにきて開発、生産を急いでいるのがSAFだ。SAFにはさまざまな製造方法があるが、その多くがバイオ資源由来であり、バイオ燃料の1つと言っても良いだろう。一般財団法人・石油エネルギー技術センター(JPEC)によると、「ニート」と呼ばれる合成燃料SAFを100%使用した航空燃料の国際規格はASTM(American Society for Testing and Materials International)で規定されているが、その中には現在最も実用化が進んでいる廃食油や獣脂などを原料とするHEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)の他にも、さまざまな製造方法があり、そのうちの1つがBBGIが活用を目指しているATJだ。2018年6月にその原料アルコールにエタノールを使ったATJが認められたことで、現在、ATJ型のSAFに対する関心が高まっているようだ。
GBEPバイオエネルギーウィークで講演したアメリカ穀物協会(USGC)のクリス・マーキー氏はSAFについて、まず「SAFの需要は今後数十年、特に北米、欧州、アジアで伸びが加速するだろう」とした上で、「アジアが最大のSAF生産地域になる」との見通しを示した。そして改めてASTMがエタノールをATJ原料にすることを認めたと強調。「エタノールは広範囲で入手可能であり、経済的にもSAFの原料として有効だ。エタノールは世界的にも生産能力の大きい既存の大規模工場を活用でき、SAFの需要拡大に対応することができ、SAFの生産・流通の技術的障害とコストを削減できる」とアピールした。
バイオ燃料と食料との競合論 BBGIのキッティポン社長はTJRIとのインタビュー で、建設中のSAF工場(バンコク・プラカノン地区)で利用する原料は、産業部門や飲食店、一般家庭から集めた使用済み食用油(廃食油)を利用する方針を明らかにする一方、バンコク・ポストの取材に対してはATJ技術を使った新原料の利用も検討していると述べた。筆者がバイオ燃料という言葉を初めて聞いた2000年ごろ、廃食油を回収してバイオディーゼル製造に挑戦していた東京都の町工場の取材をしたことがある。その時に廃食油の回収がいかに大変だという話を聞いた。廃食油の回収業という特殊な業界の難しさもあったが、そもそも、回収する際に使用する商用車の燃料代など回収コストを考えた時に採算が合うのだろうかと疑問を持った。さらに二酸化炭素(CO2)削減が国際課題となる中で、回収する際に使う燃料と排ガスは脱炭素の取り組みにどう影響するのかという問題も出てくる。
バイオ燃料の取り組みでは必ず食料との競合が批判されるが、米国のエタノール業界は、米国産トウモロコシのほとんどが飼料用であり、エタノール製造時に出る副産物DDGS(Dried Distiller’s Grains with Solubles)は飼料になると強調している。また、タイのサトウキビでも砂糖精製後に残る廃糖蜜(モラセス)やバガスからもエタノールを生産できる。BBGIのキッティポン社長はキャッサバ原料のエタノールに関して、「タイでは年間3000万トンのキャッサバが生産されているが、エタノール産業に使用されているのは約300万トンだけだ。このような状況なら人間の食料と競合せず、原料に付加価値を与える」と語っている。
米国やタイなど世界の主要農業生産国でも時には天候不順により供給不足気味になることもあるが、生産性の向上により過剰基調であり、作付面積の削減で対応することが多い。エネルギーの脱化石燃料に取り組むなら、自動車の動力源も含め、「非加食」農産物にこだわらず、改めて低コストの「バージン」のバイオ資源の価値を見直し、食料供給とのバランスを取りながら活用していくことも選択肢の一つではないか。